|
|
13.自分でホームページを運営してわかったこと
|
私の「趣味のホームページ」は1997年から2000年まで運営していた。
「がちゃぽむ」という。
いわゆるガチャガチャ。駄菓子屋やスーパーやトイざラスの店先にある、あの100円か200円程度の自販機で買える、オモチャのカプセル。
ソレをコレクションしているのだ。
知らない方は驚かれるだろうが、今のガチャガチャは非常に品質が良く、大人のマニアが大勢いるのだ。メーカー側も心得たもので、大人が喜びそうな商品を次々と出している。キャラクターものがほとんどで、昭和40年代頃にヒットしたテレビキャラクターがゴロゴロ新発売される。
ガチャガチャはクジのようなモノで、狙って買うことができない。何種類もある時は、当然、ダブリ(重複)が出てしまう。それで、ホームページを作った。
インターネットで同好の士と交換したり売却したりするのだ。
結果から言うと、かなり儲かった。
しかも、あの手の商品は一期一会、再発売されることはまずないため、あっという間にプレミアがつくのだ。200円で手に入れたモノを2万円で売却したこともある。
私自身がコレクターなので、マニアをくすぐる演出もふんだんに取り入れたサイトだった(もっとも私程度のマニア度では、ネットの濃厚なマニアたちには遠く及ばなかったが)。
1つ1つの商品には必ずコメントをつける。相手もマニアだから、当たり前の説明など必要ない。私だけの思い出とか印象を書いた。
例えば、仮面ライダーの怪人「さそり男」のコメントはこんな感じ。
「ウチの近くに大阪サンソ、という会社があるの。いつも看板をサソリと間違えちゃうの。上半身と下半身のつなぎ目がベルトで隠れるようになっている。さそり男のくせにカッコイイぞ。」
こんなモンである。バカにしているわけではない。
観ている連中は「サソリ男」が仮面ライダー初期に登場した怪人であることも、容姿も、能力も、その回がどんなストーリーだったかも、全部知っているのだ。身長、体重、足型など、私が知らない情報まで知っている可能性が高い。いや、若いマニアで「さそり男」を知らなかったとしても同じことだ。怪獣や怪人のコトが知りたいなら、ウチではなく、その手のデータベースに行くだろう。
閲覧者が知りたいのは「ガチャガチャとしてどうなんだ?、あなたはその品をどう評価している?」といったコトなのだ。
私の「がちゃぽむ」は個人的な趣味のサイトながらも、毎月平均3000件程度のアクセスがあり、一時はテレビの取材(フジテレビとテレビ東京で紹介され、テレビ東京は後に番組出演依頼もあった)さえあるほどに、認知度が上がった。メールは毎日20通くらい届いた。
ダブリを売却しているだけで、毎月10万円前後の儲けも出てしまった。あのまま続けていたら、こっちを本業にすることも出来たかもしれない。
仕事が忙しくなって夜中まで残業が続くようになって、やむを得ずサイトは停止させたが、このときの体験は、今、とても役に立っている。
通販サイトではないが、品物を送って代金を受け取る、ということも3年近くやったし、掲示板の運営、ニュースの更新、全体のリニューアル、客寄せのためのキャンペーンや特集ページまで、とにかく、いつもお客に提案するようなことを全部、やった。おかげで「ホームページを作る」のではなく続けていく大変さ、プレッシャーがわかった。
(これについては「10.毎日毎月、日記のような市議会議員サイト」に書いた)
ちょっと体験してみよう、という程度では本当のことはわからない。
3年の経験はとても大きなもので、「自分ではやったこともないネットコンサルタントのセンセイ」や「技術ばかり先行するITソリューションを売り物にする企画会社」たちとは違う。
あまりにも大人のマニアが多いので、「家族持ち専門」のコーナーも作ってみた。オモチャばかり買っている父親として、子供にどうしつけをすればいいのか、とか、呆れている(に違いない)家族に、どうやって理解してもらうか、とか、ガチャガチャをダシに仕事を獲れないか、とか。
また、我が子の成長記録と子育て日記を書いた「親ばかページ」も併設していて、そっちには主婦のアクセスもあった。ここでの「親ばか交流」が、後に「04.掲示板でお客と友だちになった子供服屋さん」の例に活かされている。
さらに、いわゆるマーケティングにも役立った。
お客のドコをつつくと、どんな反応が返ってくるか、もかなりわかったからだ。
客は知っていることは聞きたくないのだ。
他所でも入手できる記事は読んでくれない。逆に、知りたいことを教えてくれる相手には、ちゃんとお金も払ってくれる。1つ1つの品がどんなモノなのか、カタログではわからない細かい情報。
代金が回収できない、といったことは一度もなかったし、何人かの人とは実際に会って交流を深めるなどもできた。
お分かりだろうか?。
品物を売っていても、(実質的には)人は情報にお金を払っているのだ。
このことは重要だ。
ちょっと話は逸れるが、20代の頃、東京江戸川区に住んでいた。
いわゆる下町で、今でも大好きな町だ。
私は贔屓にしているビデオレンタル店があった。
もっと品ぞろえのよい大型店もたくさんあったが、人目につかない裏通りにあるその店は繁盛していた。何故か。
店主がビデオ好きなのだ。置いてあるビデオの内容をほとんど知っているから、客の要望に合った作品を選んでくれるのだ。単なるあらすじ紹介ではない、店主の思い入れや感動も交えて、話してくれる。
「悲しいことがあったんですね、では、この作品はいかがですか、私もつらいときには、この作品で元気づけてもらっています」といった感じだ。
彼とは仲よくなって、有志を募ってビデオ観賞会も開いた。それも、駄作に絞り込んだ観賞会(カスビデオ大会、と呼んでいた)で、年末に、その年観た作品中、もっとも駄作と思ったモノを持ちよって、飲みながら徹夜で観るのだ(シラフじゃやってられない。腹が減ると「ロシアンオニギリ」という、中に1つだけ--テレパッチとかチョコとか--トンデモない具が入ったオニギリが配られた)。どんなに駄作でも、有名なタイトルはダメ。これは知らないだろう、という、とっておきを持ち寄る。持ってきた者は、その見どころもアピールして解説し、そのプレゼンも評価して優秀賞を決めるのだ。
これも、彼は営業に活かしている。
発売元との関係で、駄作も仕入れなければならないことが多いからだ。絶対に客が借りそうもないタイトルを仕入れるのはリスクが大きい。だが、駄作だって楽しみ方があるのだ。
彼は観賞会そのままにプレゼンテーションする。客も「駄作だ」とわかって借りていくから苦情も出ない。「アタック・オブ・キラートマト」や「死霊のぼんおどり」があれほど回転するレンタル店は稀だろう。
後年、「裸のガンを持つ男」が劇場公開されたとき、私たちは以前に、アメリカで2週間だけテレビ放送されたバージョンを観ていたので、(一般客が気づかない)テレビシリーズを踏まえたネタでも笑うことが出来て優越感に浸っていた。
「あるモノの楽しさ」は、そのモノとは離れた場所にもついて回るのだ。
お分かりいただけるだろうか?。
カタログ的な情報ではなく、売る側の想いのつまった情報が「お金」になるのだ。
インターネットでの広報や販売はカタチがない。最終的には品物が届くとしても、購入するそのときには、単なるデータのやり取りに過ぎない。
だからこそ、それを「感情のこもったやりとり」にすべきなのだ。デジタル世界の、冷たい対応などでモノは売れない。商売をする上で、人の温かみや真心は、何よりも大切なものだと思う。
自分だけのプレゼンテーション。
やるべきことをちゃんとやれば、便利なショッピングシステムなど無くても、ネット商売できるのだ。
※もっとも、問合せやオーダーをメールで受け付ける程度の対応はできたほうがいい。直接の電話は「煩わしい」と感じる人が多いからだ。私も電話だけしか連絡方法がないところで買い物することは、まずない。
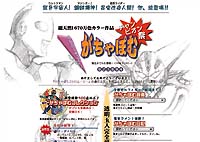 |
|
|
|
|